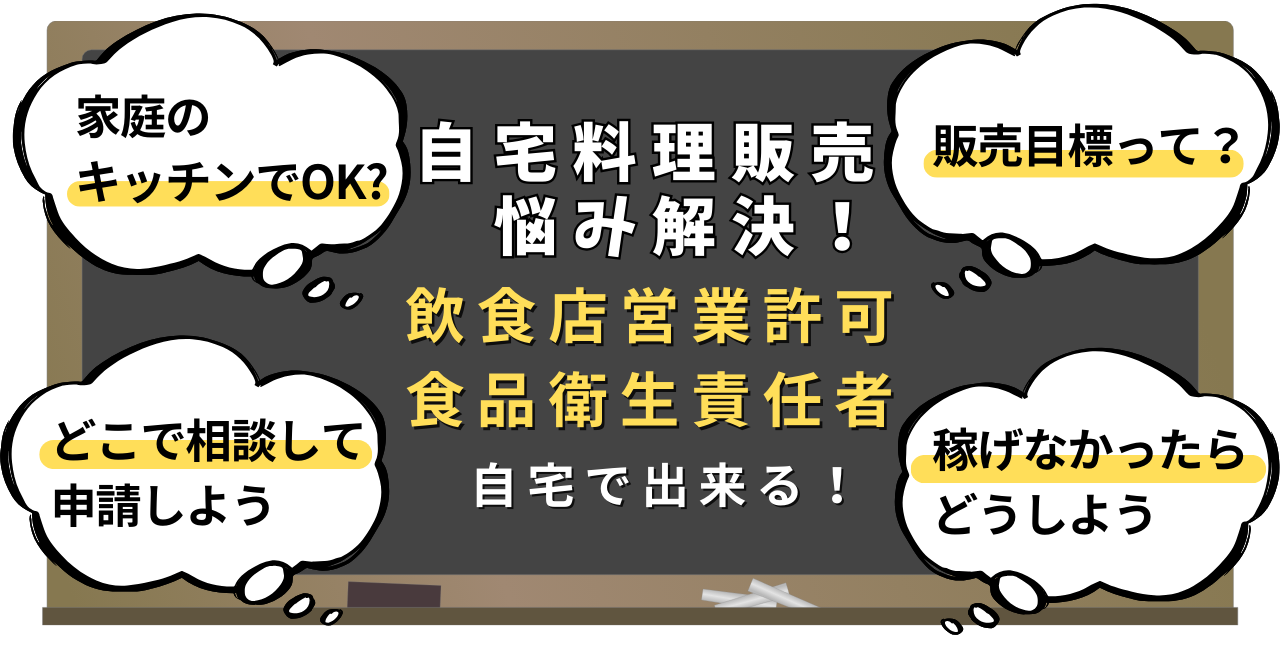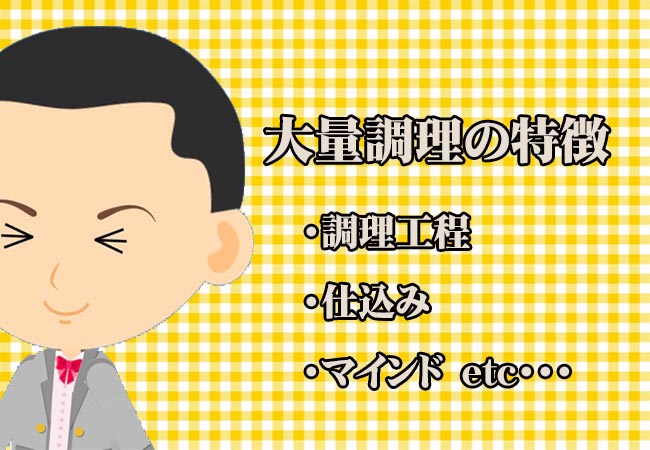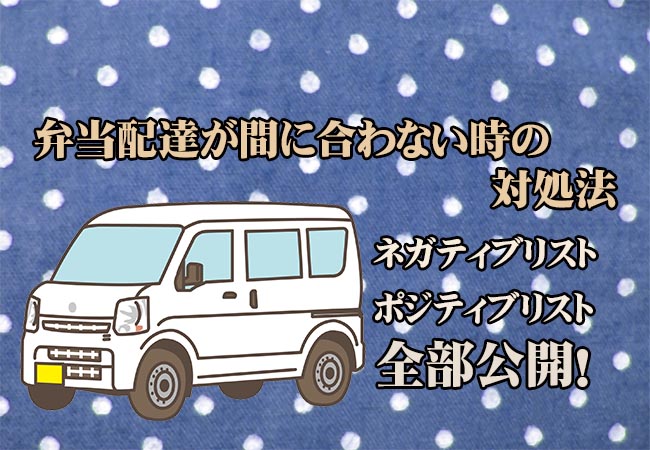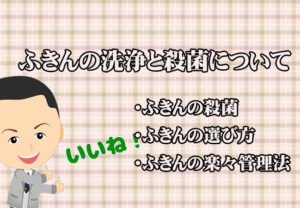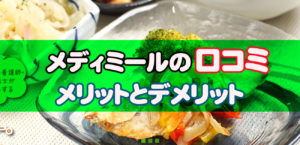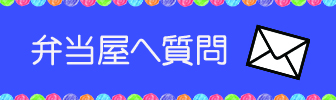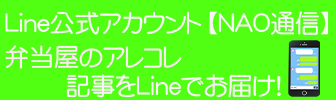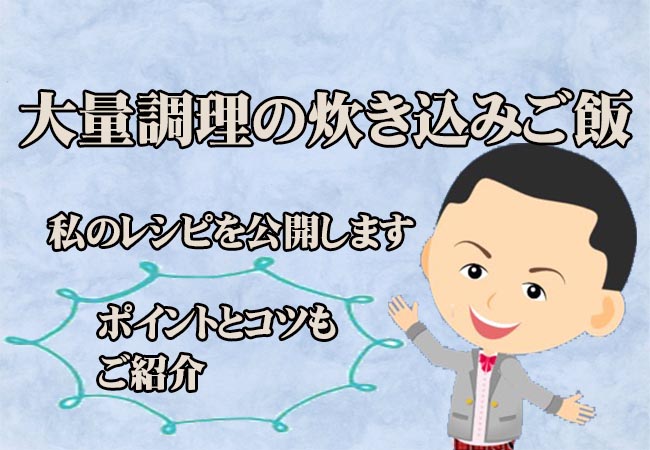
大量調理の炊き込みご飯って結構難しいと思いませんか?
米に芯ができしまったり、ベトベトになったり、味が薄くなってしまったり・・・。
炊飯器にも左右されやすいし、水分量の調節も難しかったりします。
慣れてしまえばこっちのものですが、最初の一歩が難しいかと思います。
上手に炊けないと、とてもお客様にお出しすることができない品物になってしまうのも味付けご飯です。
ですが、ご安心ください。
この記事にレシピを載せておきました。
この記事では、大量に炊き込みご飯が上手に炊けるように、炊き込みご飯レシピを始め、コツやポイントなどを話していきます。
・大量調理の調合ダレのレシピ
・大量調理の炊き込みご飯のポイント
・大量調理の炊き込みご飯のコツ
目次
大量炊き込みご飯のレシピ

私は山菜炊き込みご飯をよくやるので、このレシピを書いていきますね。
ちなみに、使用するお米は、無洗米です。(水分量注意)
・山菜水煮 2kg
・人参千切り 1kg
・油揚げ千切り 500g
・鶏コマ切れ 500g
・水 6700cc
・調合ダレ 800cc
これらを入れて、炊けば鶏山菜ご飯の出来上がりです。
使う釜はこのような炊飯釜を使います。
炊き込みご飯のポイントは、3つあります。
・水分量は少し多め
・調合ダレを使用する
ポイント1 具材は、ご飯を炊く時に全体が隠れるぐらい具を入れます
具の量を少なくすると、炊きあがったときに、「アレ、少ない・・・」って思う時があります。
山菜ごはんならどっさり入れないと山菜の感じはしません。
これは、お好みですので自分で試してやってみてください。
おススメは、具が多めです。
余談ですが、キノコなどは水分量が多いので水を入れすぎるとベトベトになります。
大量調理の炊き込みご飯の場合、ベトベトになってしまうとお客様に出せないので、キノコの使用は、自信がない方はやめておいた方がいいです。
ポイント2 水分量は少し多め
炊き込みご飯を作る時、一番困るのが「芯が残る」という状態です。
普通の炊飯の場合、沸騰によるお米の流動が激しく行われるんですが、炊き込みご飯の場合、このお米の流動がきちんとできない場合があります。
その理由としては、やはり具材が釜の中にお米と一緒に入っている為、流動がしにくい。
その為、火が通りにくく、芯が残るという状態になります。
ですので、それを補う為にも、水分を多めに入れます。
上記のレシピですと、水6700cc+調合タレ800cc=全体7500ccです。
普段の炊飯なら、5kgのお米に対して7150ccの水を入れれば大丈夫なんですが、350cc多く入れています。
これらの調節は、炊飯器の機能にもよりますので、一概には言えませんが、炊いた感じで少しずつ調節していくことが大事です。
ポイント3 調合ダレの作り方
調合ダレを作り方は以下の通り。
(大量調理の為、量が多くなります)
たまり 1800cc
酒 1000cc
みりん 10000cc
グルタミン酸ナトリウム 1000g
ざらめ 10kg
かつおだし 1kg
大量料理での炊き込みご飯の大変なところは、釜ごとに味付けを行わないといけない所です。
しかし、そんなことをしていたら、ランチの時間に間に合わなくなりますので、調合ダレを使うことで時間短縮を狙いました。
このレシピだと、かなり甘いタレになります。
実は、この調合ダレのレシピ。
当初は煮物のタレとして作ったレシピなんです。
甘口で使いやすいので、時間がない調理工程の場合先に調合ダレを作って煮物を作ったりもします。
ですので、微調整でもっといい調合ダレレシピになると思いますので、改良は可能です。自分の舌に合うものを作ればいいと思います。
アプローチとして、調合ダレは使えますよってことが言いたかったわけです。
※調合ダレが余ることが心配になると思いますが、余ったら煮物で使えるので使いまわしが出来ます。(私は煮物のタレとしても使っています)
大量の炊き込みご飯を作るコツ

大量調理の炊き込みご飯を作るコツを3つ紹介します。
大量調理の炊き込みご飯を作るコツ
✅炊飯直前に釜の中を混ぜる
✅具材は、小さい方がいい
✅鶏肉を入れる場合、加熱をしておく
炊飯直前に釜の中を混ぜる
炊き込みご飯を釜にセットする直前に一回混ぜることが大事です。
理由は、2つ。
①醤油が沈殿している為、釜の底が焦げる。
②対流しやすくなる。
しょうゆは焦げやすいので、炊飯でも注意が必要です。
炊き込みご飯をする直前に釜全体を混ぜて揚げることで、焦げを防ぐことが出来ます。
そして、対流も良くなりますので、是非、炊飯直前に釜の中を混ぜてください。
具材は、小さい方がいい
具材が、小さい方が炊き込みごはんには有利です。
理由は先ほどから出てくる、炊飯時の釜の中の対流がうまくやれるからです。
具材が大きいと重くなり、重力の力で対流がしにくくなります。
ですので、具材は小さめを推奨します。
それに、機械で盛り付ける場合、具材が機械に絡まって取れなくなるので、具材が小さい方が、盛付けもしやすいってことになります。
鶏肉を入れる場合、加熱を前もってしておく
鶏肉を入れる際は、先に湯通しを行いましょう。
鶏肉など火が通っていない具材は、炊飯前は冷蔵庫などに保存しているはずで、温度は冷たいはずです。
温度が下がった状態で、炊飯を行うと、沸点まで時間かかり上手な炊飯が出来なくなる可能性が出てきてしまいます。
そうなると、芯が残ったり、ベタベタになってしまう原因になってしまいます。
特に鶏肉などは、鮮度を保つために冷蔵庫にしっかりと保存を行う為、キンキンに冷えています。
それを、炊き込みご飯の具材と一緒に入れたらどうなると思いますか?
一気に、水の温度は下がり、いつもと同じ状況で炊飯が出来なくなってしまいます。
最悪の場合、鶏肉に火が通ってない状態で出てくる可能性があるので、鶏肉を先に火を通しておくことが大量調理の炊き込みごはんでは重要です。
(旨味はどこか行ってしまいますが・・・。)
分かっていると思いますが、炊き込みご飯でダメなこと

一応分かっていると思いますが、大量調理の炊き込みご飯でやってはいけない事を書いておきます。
夏場は腐りやすいのでダメです
夏場は、腐りやすいので炊き込みご飯はNGです。
ですので、涼しくなってから炊き込みご飯を提供しましょう。
大量調理は一回の失敗が大きなダメージになる
これもわかっていると思いますが、大量調理で失敗すると材料費など買ったお金は全部台無しになってしまいます。
企業にとってダメージが残るということです。
大量調理の場合、連続自動炊飯システムで炊いている人もいるはずです。
そうなると、一回始まってしまうと止まることが出来ません。
どんどん火の中に釜が送り込まれていきますので、失敗すると修復がしずらいです。
三連の炊飯器でも同じで、一回で大量に炊飯を行うことはリスクもあります。
ですので、炊き込みご飯を行う前は、必ずリハーサルを行いましょう。
これが大事です。大事なのでもう一度言います。
炊き込みご飯を行う前は、リハーサル!
上手にできるか確かめた上で、お客様に提供をしていきましょう。
もしダメなら・・・諦めて普通の炊飯に切り替えることも頭の片隅に入れて作業を行いましょう。
まずは、炊き込みご飯をやってみよう!
今回の記事では、
・大量調理の炊き込みご飯のレシピ
・大量調理の調合ダレのレシピ
・大量調理の炊き込みご飯のポイント
・大量調理の炊き込みご飯のコツ
などを書いていきましたが、やはり大量調理のポイントは調合ダレだと感じます。
どれだけ、旨いタレを使って調理をしていくかが、大量調理では大事になってきます。
是非、炊き込みご飯でも調合ダレなど使って上手に炊いてみてください。
ただ、ここまで書いておいて一番楽な方法は、炊き込みご飯の素を使うのが楽かな。って思います。