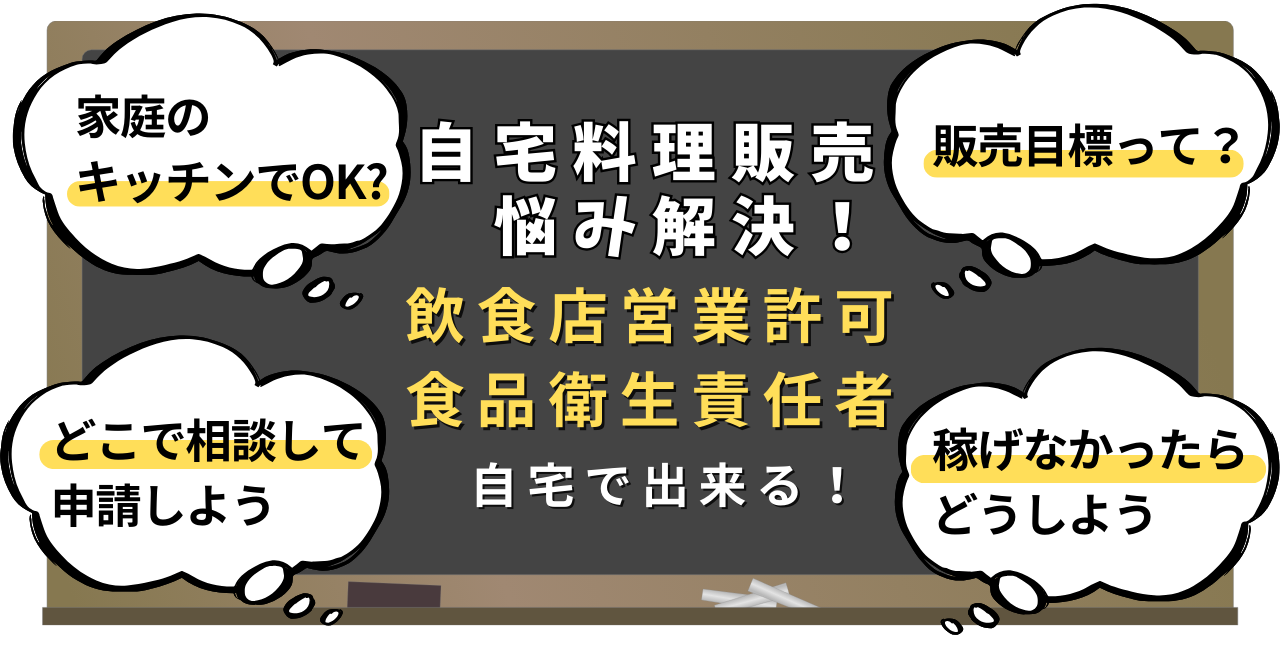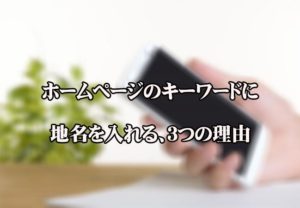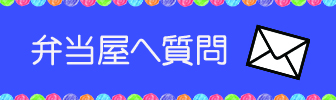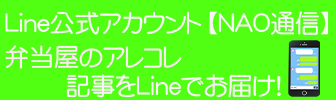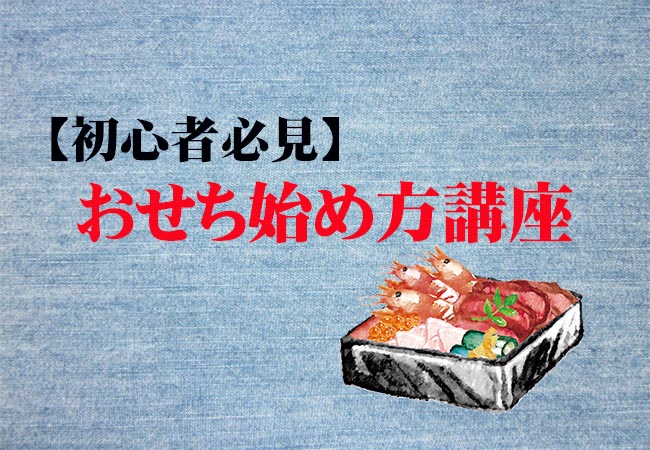
弁当屋は年がら年中忙しいけど、正月ぐらいは仕事を忘れたい・・・。
でも、弁当屋には大事なイベントが正月にあります。
そう「おせち」です。
おせちと言えば、インターネットやコンビニ、大手の百貨店など「おせちビジネス」が大いに盛り上がり、どこでも販売合戦が行われています。
そして、売った者勝ち状態。
そんな中、弁当屋もおせちを販売していいものなのかと消極的な考えを持つ方もいるかもしれないので、最初に言っておきます。
弁当屋もおせちを作って販売してもいいんです!
しかし、この「おせちビジネス」。始めるにも基本的なおせちについてのノウハウがないと出来ません。
もし、おせちビジネスのノウハウがないと、記憶に新しい「おせちスカスカ事件」のような大問題になってしまいます。
ですので、「おせちやってみようかなぁ」という人は、ある程度の基本的な知識を付けてからおせちビジネスを始めましょう。
この記事では、「おせちビジネスの始め方講座」ということで、おせちについて基本的なことを学べるページにしますので、最後まで読んでください。
この記事で分かる事
・おせちを販売することで大事なこと
・初年度のおせちの販売の考え
・初年度の目標数値の考え方![]()
目次
おせちビジネスのスケジュール

おせちビジネスで大事なのが、スケジュールです。
スケジュールを間違えると、おせちに使う食材が手に入らない!っていう事態にもなりかねません。
まずは、おせちに向けたスケジュールの管理を知って、計画を立てる事が重要です。
以下が、おせちのスケジュールの見本です。
| 3月 | おせちのスケジュールを立てる |
| 4月 | おせちの予算を決める |
| 5月 | 昨年のおせちの情報を集めて研究 |
| 6月 | 引き続き研究。料理の選定に入る。 |
| 7月 | おせちの器を決める |
| 8月 | おせちの料理を決定 |
| 9月 | チラシを作製。おせちの器の発注。おせちの材料発注。 |
| 10月 | おせちの販売に入る。 |
| 11月 | おせちの販売を徹底的にする。11月末には受注を行う。 |
| 12月 | 本番準備。 |
ザクっとしたおせちを販売するスケジュールを立てた後は、これを月ごとに細分化していきます。
表を見てわかると思いますが、1年かけて準備をして販売していくのが「おせちビジネス」です。
このおせち販売のスケジュールに関しては、「販売個数が少ない」とか、「店の規模が小さい」とかは関係ありません。
すべてのおせちビジネスをする人が、1年をかけて作り上げていくものなんです。
おせちは一般的に「年末行事」ですが、ビジネスと考えたとき「年中行事」ということになります。
その認識をして仕事を進めないと、以下のような悲劇が起こります。
おせちの悲劇✅目標の販売個数が売れない。
✅食材が手に入らない。
特に、「おせちビジネス」を始めようとしている人には、昨年末のデータがありません。
まず、基本的なスケジュール管理を知って、慎重に進めるべきでしょう。
最初の一年目、販売個数を決める

初年度の販売個数を決める時に、夢のような個数を販売計画をしてはいけない。
現実からかけ離れた、販売個数は失敗のもと。そして、失敗した時、ダメージが残ります。
確かに、売上を作りたい!っていう焦る気持ちで、途方もない販売個数を設定したいかもしれない。
売り上げたい気持ちは商売人なら誰しもあるもの。それはしょうがないけど、冷静になりましょう。
だいたい、初年度の人は前年度の実績がないわけで基準にするべきデータがないわけで、基準がないのに、何を物差しにして販売個数にするのでしょうか。
人が販売している個数ですか?
自分が売り上げたい金額ですか?
それとも、自分が抱えているお客様の数ですか?
そんな数は、販売できるまでは、そんな数は当てになりません。
当てになる基準は、自分で作った販売数だけです。
まずは実績を作る事です。
無理なく販売出来て、無理なく作れる数を基準にして実績を作る。
そして、来年に繋げる。それが、おせちビジネスです。
恥ずかしい話ですが、私も初年度の販売個数は、20個でした。
販売金額は、1台、11,500円。売上にして、230,000円。
それでも、作るのはバタバタだし、売るのも慣れないので苦戦しました。
しかし、そのデータをもとに翌年度は5倍以上は売り上げました。
おせちの原価について
おせちを販売するにあたって大事になってくるのが、材料費。原価です。始めておせちを販売する場合、原価の考え方が気になる所です。
答えを言ってしまうと、原価率30%が理想です。しかも、材料費+器で、原価率30%を実現したいです。その為に必要になってくるのが、付加価値になってきます。
おせちで原価率を下げることは簡単です。高値で売るだけです。1万円のおせちを2万円で販売出来れば、原価率は下がります。
原価率を下げる為に、頭を使わないといけないんです。ここがポイントです。
他のお店のおせちを見たことがありますか?いろんな付加価値を付けて販売していることが分かります。有名なシェフが作ったおせち、高級ブランドのおせち、など付加価値を付けて高く販売することによって、原価率を下げる算段をしています。
では、おせちを始めて作る人たちは、どうやって付加価値をつけるべきなのでしょうか?これがおせちビジネスの最初の参入障壁となります。普通に販売すれば、おせちの材料費だけで原価率30%+器の値段(1000円以上は当たり前)です。よって、儲けることが出来ない。売値を高くする必要があるんです。
その為の付加価値として、初年度は以下のような提案していくと付加価値になります。ちなみに、以下の意見は自分の会社の職員によるミーティングで出た意見です。参考になれば幸いです。(突拍子もない意見もあります。ご注意ください)
おせちの付加価値になる要素
✅他の店で使わないおせち食材の使用
✅地元の有名ブランド食材を使用
✅雇っている管理栄養士をブランド化して使う
✅料理研究家としてスタッフの誰かをブランド化
✅圧倒的に綺麗に写真を撮影
✅チラシの構成で高く見えるように工夫
✅知り合いの有名人に手伝ってもらう
✅通常のおせちではなく、お年寄り専用のおせちを作る
✅歯がないお年寄りが食べるおせちを作る
ちょっとふざけている感じはありますが、実際に出た意見ですので参考程度でお願いします。しかし、私はこれらの意見の中から採用した付加価値があります。一人で考えるよりもみんなで考えた方が意見がたくさん出るので、おせちはみんなで考えましょう。
おせちの器の決め方

おせちの器選びは、自分のイメージを表現するためにも大事!
でも、おせちの器を決める時期に包材屋に行ってもおせちの器は販売されていません。
なぜかと言うと、おせちの器を決めるのは7月。
おせちからかけ離れた月だからです。
そんな時期から、おせちの事を考えているのは、おせちをビジネスに考えている人ぐらいですので、器を探すのも一苦労です。
しかしながら、おせちの器を販売している業者はどこかにはいます
おせちの器は、包材の卸問屋を介して手に入れる事が出来ます。
包材問屋と仲良くしていると、サンプルを手に入れる事が出来ます。
おせちの画像を包材問屋に見てもらい、「こういうのを作りたい」と言えば、少なからずとも近いものを手配してくれるはずです。
2年目になれば、器の情報も多くなるはずです。
まずは、初年度は自分のイメージをぶつけること、つまりチャレンジすることが大事でしょう。
割引とリピート

初年度、おせちの販売個数を伸ばすのは、実は簡単ではありません。
とにかく実績がないので、上手には売れないでしょう。
それは覚悟しておいた方がいい。
実績はお客様も見ているところで、ほとんどのお客様は、「去年のおせち良かったから、またあれ買おうよ」と、リピートに走ります。
しかも、始めておせちを販売した場合、「大丈夫なの?」っていう心配にもなります。
それは、やはり金額が大きい買い物だからでしょう。
少なくとも、1万円以上のおせちを作りたいし、販売したいですからね。
もちろん、お客様もそれぐらいの金額のおせちを探し求めています。
金額も大きので、お客様のおせちの選定も慎重になるのは当たり前でしょう。
そこで大事なのが販売を促進するための起爆剤です。
例えば私がやった起爆剤は、
✅引き取りの場合、1000円キャッシュバック
✅11月中に買ってくれたら、1000円キャッシュバック
など。
他にも、ありますが、この辺りがやりやすい販売促進でしょう。
一見、割引ばかりだと儲からないと思いますが、おせちの原価も計算すると、3割の材料費で、7割は儲けになります。
1000円の販売促進費なら安いものです。
しかも、販売促進は来年のリピートにもつながります。
先ほども言いましたが、「去年もここで買ったからまた買うか」って言うのが「おせち」です。
まず、知ってもらって買ってもらうことが大切です。
それと、初年度、おせち販売で大事なのが「無理なく販売する」事です。
従業員もおせちビジネスは初めての事。
力を入れすぎると、期待に変わります。
期待を裏切られると、人は信頼をしなくなります。
しかし、期待以上の成果があると人は、おせちへの信頼を勝ち取り、「来年は100台販売して儲けてやる」という想いにもなります。
無理な販売や製造はしこりとなって残ります。
従業員も人ですので、心のコントロールは大事です。
そういうところもケアしながら、おせちビジネスを行いましょう。
おせち食材の仕入れは無理なくやる

おせち食材は、12月に入ると手に入りにくくなります。
黒豆を仕入れたくても、「在庫がないので無理です」っていう可能性もあります。
これは、本当の話で私も何回か困ったことがありました。
すでに、写真やチラシは9月に終わっています。
お客様も年末のおせちを楽しみにしていますので、食材の在庫がないでは済まされないので、慎重になるべきでしょう。
困難な状況を避ける為に、初年度のおせち販売個数は無理ない販売個数に設定すれば、危険な問題は少なくなります。
全部手作りでも出来る販売個数にすれば、材料を9月ごろから手配すれば必ず間に合いますし、無理のない個数なら食材は手に入るはずです。
とにかく、無理のない個数を販売することが大事。
初年度は慎重になるのが鉄則でしょう。
調理場が混乱しなようにする

「おせちを作ったことがあるという経験値」は大事です。
調理場に、おせちを作ったことがあると言う人がいるだけで、プラス材料になります。
初年度、おせちを作るのに大事なのが計画的に作れるかどうかということです。
調理は、段取りがすべて。
段取りが出来ない状態でおせちを作ることは、自滅行為です。
調理場の混乱を招くし、調理場で働く人の信頼も失います。
ですので、おせちを販売するにあたって調理場との連携は不可欠。
混乱がないように、論理的に調理の組み立てを計画することが大事です。
初年度は、自分でチラシを作ろう

おせち販売の初年度は、売上は少ない。
先ほども言いましたが、私の初年度は20台程度で、売上も20万ぐらい。
売上だけでは、写真撮影代や販売促進費にまで手が回らないでしょう。
よって、おせちの写真撮影やチラシ作成に予算をかけていられませんでした。
幸い私は、商品写真の撮り方や写真を加工する方法、チラシを作るソフトを扱えるため、自力でチラシを作り販売促進を行いました。
しかし、いきなり、これらを出来るようになるのは至難の業。
やはり、チラシはプロに頼むことが近道と言えます。
しかし、写真だけは自力で撮影したいものです。
写真をプロに頼むだけでも、かなりの費用が発生する為、避けたいところです。
自分で撮影できる腕があれば、それで事足ります。
けど、写真も素人が撮った物と、ちょこっと学んだ人では雲泥の差です。
写真撮影に置いて学ぶ事は本当に大事です。
私が学んだのは、ネットで見つけたDVD写真撮影講座でした。
写真撮影の基本が身に付くし、プロのカメラマンを呼ぶ必要性もないので、講座を受講して本当に良かったです。
私が受けた写真の撮り方講座はコチラ↓
この売れる写真の撮り方講座を使って、写真撮影を行うんです。
そして、綺麗な写真を自分で撮る。
それだけでも、随分な経費削減になります。
写真を撮ったら、後は写真を使ってチラシを作成するだけです。
今の時代、写真はデータ化出来て、チラシを作成する会社に渡すだけで、チラシを作成してくれますよ。だから、まずは写真が大事。
そして、自分で撮影することが大事!
最初の一年目、おせちビジネスを成功させる大切さ

以上のように、おせちビジネスで大事なことを書いていきました。
大事なのは、スケジュールを決めてキッチリと行うことです。
おせちビジネスは、努力と辛抱の賜物なんです。
一朝一夕では出来ませんが、儲かる方法を見つけることが出来れば、1年のこの時期だけで商売が成り立つという、驚異的な商売方法にもなります。
極めてみると、一生涯のビジネスにもなります。
写真の撮り方を学ぶなら撮影教材!
【筆者も写真教室に通うことなく撮影技術が身に付きました】
初心者でも解説に従って撮影すれば、魅力的な写真を撮れる!
写真教室に通うより、圧倒的に安いし、上達も早いですよ